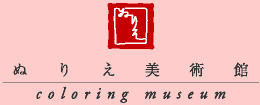« 追悼のお花 | メイン | 永遠なりきいちのぬりえ展(2) »
永遠なりきいちのぬりえ展(1)
昭和のぬりえ作家 蔦谷喜一追悼展
開催期間:平成17年3月12日(土)~5月29日(日)
_15.jpg)
平成17年2月24日、91歳で老衰のため蔦谷喜一が永眠いたしました。2月18日に91歳の誕生日を迎えたばかりでした。
蔦谷喜一という昭和のぬりえ作家が伯父であるということが、私にとってこのぬりえ美術館を開館するきっかけでした。
戦後の少女、団塊世代の少女にとって、ぬりえは欠くことのできない遊びでした。「ぬりえが宝物だった」と表現してやまない昔の少女たちがどれほどいることでしょう。ぬりえから沢山の夢をもらい、貧しいけれど心豊かに、情緒や仕草を学んでこれたことでしょうか。
ぬりえは子供の遊びですが、心を育む遊びでもあります。きいちは、「塗らなくてもいい、美しい絵を持ってもらいたい」と言って、美しい、本物の絵を描いていました。
少女にとって大切な宝物をこれからも残して、ぬりえ文化として育てていきたいと思ってこのぬりえ美術館を開館しました。ぬりえ美術館の使命はこれからです。
永遠なりきいちのぬりえ!!
蔦谷喜一の残した作品を、どうぞ心ゆくまで楽しんでいただきたいと思います。そしてこれからも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
きいちの仕事
きいち(本名蔦谷喜一)は、大正3年京橋区に紙問屋を営む「蔦谷音次郎商店」の5男坊、7番目の子どもとして生まれる。商売は隆盛を極め、経済的に恵まれた生活を送る。きいちは絵が好きで、特に人物を描くことが得意な少年だった。
昭和6年(1931年)17歳の時、上野の帝展で特選をとり評判になっていた山川秀峰(やまかわしゅうほう)の「素踊」に心酔し、川端画学校で日本画を又クロッキー研究所にも通い、絵の勉強を始めることとなる。
昭和15年(1940年)26歳の時、友人が持ち込んだ「ぬりえ」の仕事をアルバイトのような気分で始める。絵は姉妹とよく見ていた歌舞伎をテーマにしたもの。この当時の名前は、夏目漱石の「虞美人草」の藤尾が好きだったので「フジヲ」である。昭和16年に戦争が勃発。世の中はぬりえどころではなくなり、フジヲ時代は長くは続かなかった。
_15.jpg)
●絵は、フジヲ時代のぬりえの「お舟」
昭和20年(1945年)敗戦。
昭和21年(1946年)柔道家の兄の紹介で駐留中の軍人の恋人の肖像画を描く。
きいちのぬりえのバタ臭さは、この時代の影響もあるかもしれない。
昭和22年(1947年)自分でぬりえを作り販売を始める。名前はキイチ/KIICHI。
その後石川松声堂と山海堂との共同経営を経て、昭和23年(1948年)に、「きいち」の名で、絵描きとしてぬりえを描くことに専念することとなる。
ぬりえはそれまでは、バラ売りをされていたが、昭和23年頃から、袋入りで販売されることになる。これは絵はがきを扱っていた石川松声堂のアイデアだったそうだ。一袋に最初は12枚セットで5円。それから物価の上昇に伴い10枚、8枚、ぬりえの人気が衰退してきた昭和40年ころは5枚入りとなった。
戦後のベビーブームもあり、ぬりえの人気はうなぎのぼり。昭和30年代後半までぬりえ人気が続く。
ぬりえ専門の絵描きの「きいち」が描くぬりえは、マンネリすることもなく、平均すると月100万セット。昭和30年前後の最高時には月160万セット売れたそうだ。
(『日曜研究家』)。
「きいちのぬりえ」は毎週新しいものが、石川松声堂と山海堂の2社から販売された。100万セットということは、毎週1つの袋入りが10万セット以上売れていたということになるわけで、10万人以上の少女が毎週きいちのぬりえを描いていたという数字になる。
そのため、この美術館のぬりえを見て、「この絵は、塗ったような記憶がある」と何人もの来館者が言うことがあり、それだけ共感性も大きいのだと感じている。
投稿者:Nurie |投稿日:05/03/20 (日)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
/721