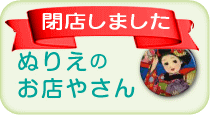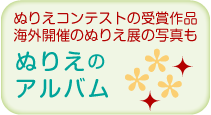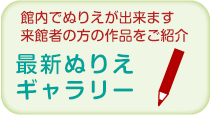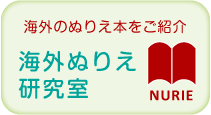12月の美術館便り
師走になりました。毎年一年があっという間に過ぎていくという感じを持ちますね。きいちのぬりえの頃は、もっと時間があったように思います。何事も気ぜわしい時期になりますので、深呼吸を一つして、お元気にお過ごしください。
さて、今月は、昭和40年代に消えてしまったきいちを発見して、再び世に送り出してくれた元文化屋雑貨店の長谷川義太郎さんの「きいちの思い出」を長谷川さんの本からご紹介いたします。
蔦谷喜一さんは、足の太い、目玉くりくりの女の子を描いていた「ぬりえ」のきいちさんである。
かつて駄菓子屋さんの隅っこでほこりにまみれた極彩色の袋に入って売られていたぬり絵は、男の子の世界にはない妙に色っぽいものに見えた。・・・・果たしてどんな人が描いているのだろうと思っていた。生きておられるのだろうか、そんな気持ちがきいちさんに会おうと思ったきっかけだった。蔵前の問屋さんやぬり絵の版元でたずねて、やっと上福岡に住んでおられることがわかった。
それとともに、何軒かの蔵前のおもちゃ問屋さんを実際にたずねてみて、ただ「きいち」とだけネームの入ったすごろくや、ノート型になったきせかえ、クレヨンセットなどがまだ作られ売られていることがわかったのだ。例によって犬も歩けば棒にあたる気持ち。きせかえのサラリーマンのお父さんは刈り上げでステテコ姿、着かざったお母さんのスリップ姿は色っぽく、そしておふとんやテレビや冷蔵庫も、なんとあの懐かしの「きいち」しているのには驚いた。
きいちさんはその描くところの少女のように、まつげの長いおじいさんだった。
「長谷川さんみたいな若い人が、どうしてわたしの絵がいいというのかわかりません」と首をかしげておられた。・・・・
「ぬり絵を描く前は人間が好きで日本画をやりたかったんですよ。でも川端画学校にいったら草や葉っぱばかし毎日描かされて、やになってやめてしまったんです。その時ぬり絵をたのまれて、それがいつの間にか本職になってしまったんですが、やっぱり日本画にコンプレックスみたいなものがあったんでしょうか。ずいぶん悩みましたね。もちろん今でも日本画を描いていますよ」
「でもぼくとしては「きいちのぬり絵」は今の世の中でも、ディレクト次第で充分生かされるとおもいますけれどねえ」
「いまの人には受けないとおもいますよ」
ぼくの悪いくせなのだ、はじめに「きいちのぬり絵」ありきなのだが、こうして話しているときいちさん本人の方へ興味の対象がうつってしまうのである。「きいちのぬり絵」はきいちさんにとっても過去のものであるらしい。「今のわたしをみて下さったらうれしいのですが」と言われると一言もないのだ。
こんな素晴らしいぬり絵があったんだと、世の中に記してもらい思ったのがそもそもの発端だった、雑貨屋を始めたことで知り合ったマスコミの人たちにも紹介して、きいちさんのぬり絵はいくつかの雑誌にも載り反響もなかなかのものだった。銀座のど真ん中で展覧会も開催され、単行本も出た。大勢の人が懐かしいと手紙もくれた。
でもこれからのきいちさんに期待してほしい。
「わたしも何年か前から病気をしましてまいっていましたが、何かこれからやっていけるような気がします」 きいちさんも言ってくれた。
世間でもう一つ価値が低いと見られているもの、あるいは認められていないものの中にキラキラ光るものが沢山ある。影響力の強いこの裏文化というやつが、もっとみとめられるようになるまでは、ぼくはこの仕事を辞められない。
「きいちのぬり絵」もこれぞ全て、それぞ一番と思っているわけではない。でもこれがなけりゃこの世は闇だ。文化屋雑貨店のものは一番でもなけりゃ、グッドデザインマークでもない。てやんでえ最高なんです。アホなのです。
白い綿のオープンシャツを初めとする基本的なものと、スーベニア文化に代表されるまがいものとが商品の核となり、そして人をだましても食いぶちをかせごうといういじましさ、これが文化屋の誇りなのである。
~「がらくた雑貨店は夢宇宙」 長谷川義太郎著 晶文社~
こうして長谷川さんはきいちを探し出し、昭和53年(1978年)に銀座の資生堂ザ・ギンザアートスペースで「キイチのぬり絵」展が開催され、この展覧会を期にきいちの第二次ブームなるものが生まれ、きいち人気は今に続いているのです。
この展覧会では、きいち所蔵のぬりえと上野の版元が所有していた原画とぬり絵を借用して展示をした。さらに、ぬり絵の復刻版をつくり、子どものころ、ぬり絵遊びをして小森和子さん、白石かずこさんなどにぬってもらった。また一般にお客さまにも復刻版を提供し、ぬり絵を制作してもらい、会場に展示した。ドイツ文学者、池内紀さんの「ぬり絵」に関するエッセイを会場入り口に展示。キイチファンであったグラフィックデザイナー佐藤晃一さんんがデザインしたポスターを会場入り口の装飾とした。その後、全国でキイチのぬり絵展が開催された。と「資生堂ザ・ギンザアートスペースの25年」の本に書かれています。
当時資生堂の商品開発部に在籍していた私は生でこの展覧会を見ています。(館)
カテゴリー
- お知らせ[66]
- ぬりえギャラリー[637]
- ぬりえサロンギャラリー[114]
- アルバイト募集[1]
- トピックス[192]
- 大人のぬりえサロン[45]
- 寄贈・寄託[22]
- 来館者の声[20]
- 海外ぬりえ研究室[20]
- 私の好きなきいち[6]
- 美術館だより[82]
- 美術館ニュース[222]
- 館長室から[3]
最近のエントリー
- ぬりえ美術館は2022年10月30日に閉館いたしました。
- 「きいちのぬりえ」本 多少在庫ございます。
- Webショップ「ぬりえのお店やさん」は本日閉店致しました。
- 10月の美術館ニュース(2)
- 10月の美術館ニュース(1)
- 9月の美術館ニュース(2)
- 9月の美術館ニュース(1)
- 美術館20周年記念誌制作アンケート【受付終了】
- 8月の美術館ニュース(2)
- 8月の美術館ニュース(1)
 12月の美術館ニュース(2)
12月の美術館ニュース(2)